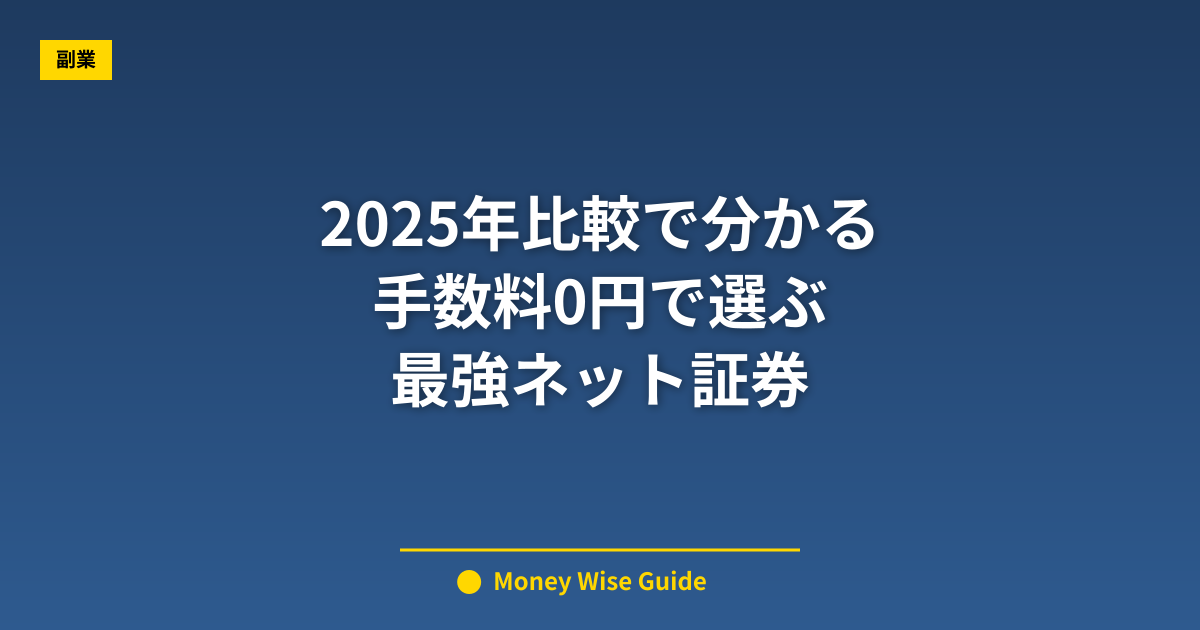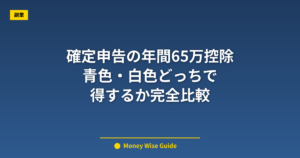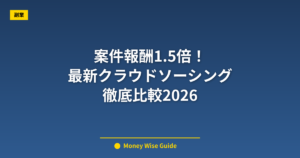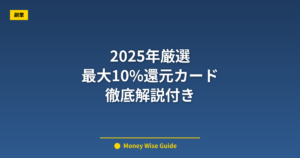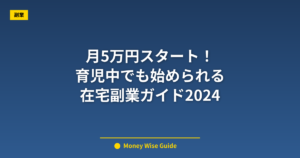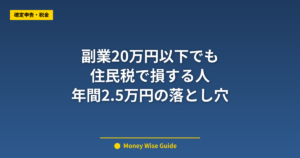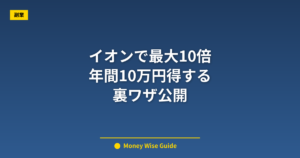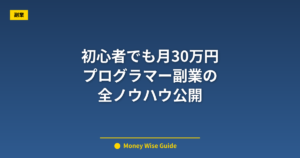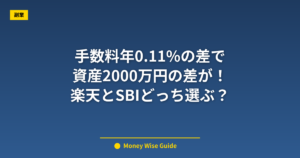【2025年最新版】楽天証券 vs SBI証券徹底比較!初心者から上級者まで完全ガイド
ネット証券業界で圧倒的な人気を誇る楽天証券とSBI証券。2025年現在、どちらを選ぶべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、両社のサービス内容、手数料、使いやすさなどを詳細に比較し、あなたに最適な証券会社選びをサポートします。
基本情報とサービス概要の比較

まずは楽天証券とSBI証券の基本的なサービス内容を比較してみましょう。
楽天証券の特徴
- 口座数:900万口座突破(2025年12月時点)
- 楽天グループとの連携サービスが充実
- 楽天ポイントが貯まる・使える
- マーケットスピードⅡによる高機能取引ツール
- 投資信託の取扱銘柄数:約2,600本
SBI証券の特徴
- 口座数:1,200万口座突破(2025年12月時点)
- ネット証券シェアNo.1の実績
- Vポイント、Pontaポイント、dポイントなど複数のポイントサービスに対応
- HYPER SBIによる本格的な取引環境
- 投資信託の取扱銘柄数:約2,700本
どちらもネット証券の大手として、充実したサービスを提供していることがわかります。特に投資信託の取扱銘柄数では、SBI証券がわずかに上回っています。
手数料体系の詳細比較

投資において手数料は重要な要素です。2025年現在の両社の手数料体系を詳しく見てみましょう。
国内株式取引手数料(現物取引)
両社ともに「いちにち定額コース」で100万円まで無料となっています。
- 楽天証券:いちにち定額コース 100万円まで0円
- SBI証券:アクティブプラン 100万円まで0円
投資信託購入時手数料
両社ともにノーロード(購入時手数料無料)の投資信託を多数取り扱っています。
外国株式取引手数料
米国株式取引では以下のような違いがあります:
- 楽天証券:約定代金の0.495%(最低手数料0米ドル、上限手数料22米ドル)
- SBI証券:約定代金の0.495%(最低手数料0米ドル、上限手数料22米ドル)
基本的な手数料体系は両社ともに非常に競争力があり、大きな差はありません。ただし、取引頻度や投資スタイルによって有利な証券会社が変わる場合があります。
ポイントサービスとお得度の比較

現代の投資において、ポイントサービスは見逃せない要素となっています。
楽天証券のポイントサービス
- 投資信託保有により楽天ポイントが貯まる(残高10万円につき月2-4ポイント)
- 楽天ポイントで投資信託の購入が可能(月5万円まで)
- 楽天市場でのSPU(スーパーポイントアッププログラム)対象
- 楽天カードでの投信積立で1%ポイント還元(月5万円まで)
SBI証券のポイントサービス
- 投資信託保有によりポイントが貯まる(残高1000万円未満:年率0.1%、1000万円以上:年率0.2%)
- Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALマイルから選択可能
- 三井住友カードでの投信積立で0.5-5.0%ポイント還元(カードランクにより変動)
- 国内株式取引でもポイントが貯まる
楽天経済圏を活用している方は楽天証券、複数のポイントサービスを使い分けたい方はSBI証券が有利と言えるでしょう。
取引ツールと使いやすさの比較
投資の成功には優れた取引ツールが不可欠です。両社の主要ツールを比較してみましょう。
楽天証券の取引ツール
- マーケットスピードⅡ:高機能デスクトップアプリ
- iSPEED:スマートフォンアプリ
- 楽天証券ウェブ:ブラウザベースの取引画面
マーケットスピードⅡは、豊富なテクニカル指標と見やすいチャート機能で多くの投資家に支持されています。特に、リアルタイムでの情報配信と直感的な操作性が魅力です。
SBI証券の取引ツール
- HYPER SBI:プロ仕様の高機能ツール
- SBI証券株アプリ:スマートフォン向けアプリ
- WEB画面:ブラウザでの取引環境
HYPER SBIは、より詳細な分析機能と豊富な情報量が特徴で、上級者向けの機能が充実しています。
初心者へのおすすめ度
初心者には楽天証券の方が使いやすいとの声が多く聞かれます。一方、SBI証券は機能の豊富さで上級者に好まれる傾向があります。
投資信託とつみたてNISAの比較
長期投資の要となる投資信託とつみたてNISAでの両社の特徴を見てみましょう。
投資信託の取扱い
- 楽天証券:約2,600本の投資信託を取扱い
- SBI証券:約2,700本の投資信託を取扱い
どちらも主要な投資信託は網羅しており、eMAXIS Slimシリーズなどの低コストインデックスファンドも充実しています。
つみたてNISAの特徴
楽天証券のつみたてNISA:
- 楽天カードでの積立で1%ポイント還元
- 楽天ポイントでの積立投資が可能
- 100円から積立可能
SBI証券のつみたてNISA:
- 三井住友カードでの積立でポイント還元
- 毎日積立も選択可能
- 100円から積立可能
両社ともに少額からの積立投資が可能で、長期投資をサポートする環境が整っています。NISA つみたて投資枠のおすすめ銘柄を選ぶ際も、両社の豊富な選択肢から最適なファンドを見つけることができるでしょう。
外国株式と海外投資の比較
国際分散投資を考える投資家にとって、外国株式の取扱いは重要な要素です。
取扱い市場
楽天証券:
- 米国株:約5,000銘柄
- 中国株:約1,600銘柄
- アセアン株:約240銘柄
SBI証券:
- 米国株:約6,000銘柄
- 中国株:約1,300銘柄
- 韓国株:約60銘柄
- ロシア株:約50銘柄(取引停止中)
- ベトナム株:約350銘柄
- インドネシア株:約70銘柄
- シンガポール株:約40銘柄
- タイ株:約70銘柄
- マレーシア株:約40銘柄
外国株式の取扱いでは、SBI証券が圧倒的に豊富な選択肢を提供しています。特に新興国株式への投資を考えている方には、SBI証券が有利でしょう。
為替取引
両社ともに外貨建て取引時の為替手数料は米ドルで1ドルあたり25銭と同水準です。ただし、SBI証券では住信SBIネット銀行との連携により、より有利な為替レートでの取引が可能な場合があります。
サポート体制とセキュリティの比較
安心して投資を続けるためには、充実したサポート体制とセキュリティが不可欠です。
カスタマーサポート
楽天証券:
- 平日8:30-17:00の電話サポート
- AIチャットによる24時間対応
- メールでの問い合わせ対応
- 投資相談サービス
SBI証券:
- 平日8:00-18:00の電話サポート
- 土日も一部サービスで対応
- チャットサポート
- 豊富なFAQと動画コンテンツ
セキュリティ対策
両社ともに以下のようなセキュリティ対策を実施しています:
- 二段階認証の導入
- SSL暗号化通信
- 不正アクセス監視システム
- 定期的なセキュリティ診断
どちらも金融機関として十分なセキュリティレベルを維持しており、安心して利用できます。
まとめ:あなたに最適な証券会社の選び方
楽天証券とSBI証券の詳細な比較を通じて、それぞれの特徴が明確になりました。最終的な選択は、あなたの投資スタイルや利用したいサービスによって決まります。
楽天証券がおすすめな人
- 楽天経済圏をフル活用したい方
- 楽天ポイントを投資に活用したい方
- 使いやすいツールを重視する初心者
- 楽天市場での買い物が多い方
SBI証券がおすすめな人
- 豊富な投資商品から選択したい方
- 外国株式投資を本格的に行いたい方
- 複数のポイントサービスを使い分けたい方
- 高機能な取引ツールを求める上級者
2025年現在、どちらの証券会社も優れたサービスを提供しており、「間違った選択」はありません。重要なのは、自分の投資目標と利用スタイルに合った証券会社を選ぶことです。
また、両方の口座を開設して使い分けるという選択肢もあります。例えば、メイン口座として楽天証券を使い、外国株式投資はSBI証券で行うといった使い分けも可能です。長期的な資産形成を考える場合は、つみたてNISA 20年後の出口戦略も併せて検討しておくことが重要です。
投資は長期的な視点が大切です。手数料やサービス内容は時代とともに変化するため、定期的に見直しを行い、常に最適な環境で投資を続けられるよう心がけましょう。また、iDeCo 掛金上限の2025年変更など、税制優遇制度の活用も資産形成において重要な要素となります。あなたの資産形成の成功をお祈りしています。