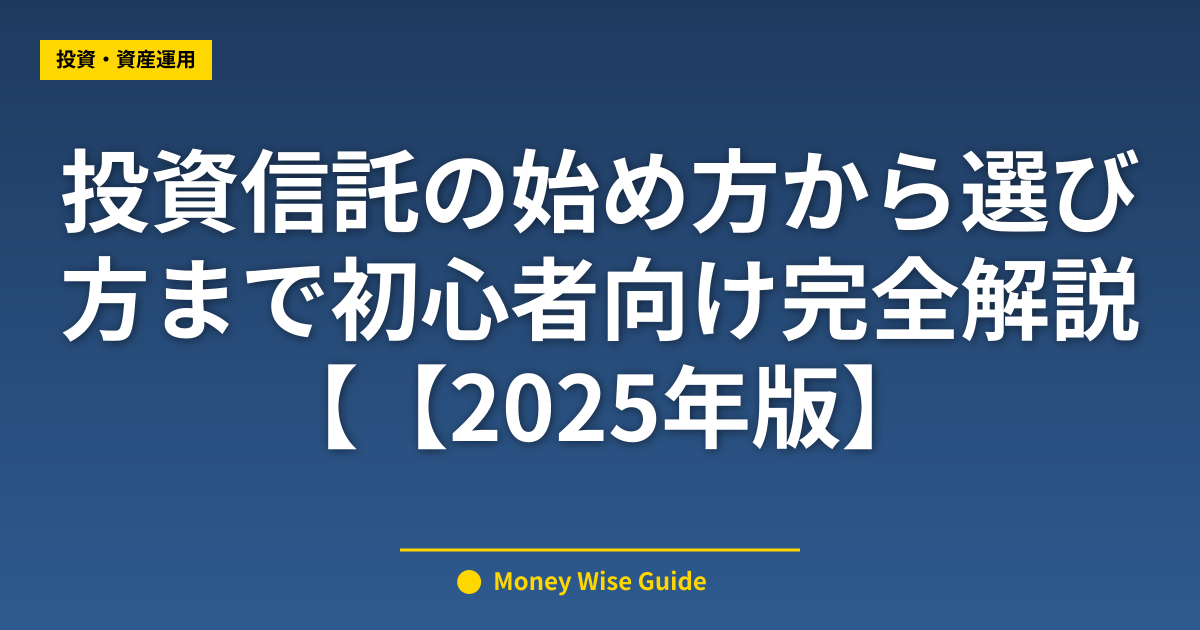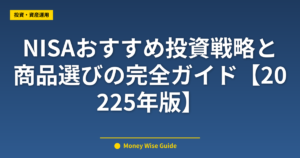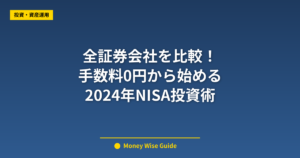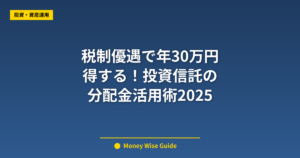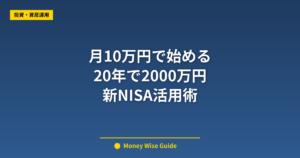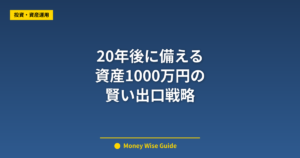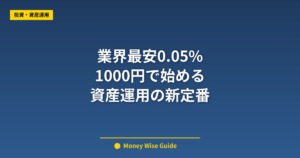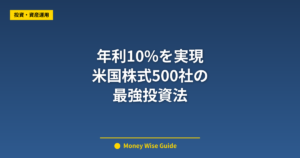投資信託の始め方から選び方まで初心者向け完全解説【2025年版】
投資に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない。そんな方におすすめなのが投資信託です。2025年現在、新NISA制度の拡充により、投資信託への注目はさらに高まっています。投資信託は少額から始められ、プロが運用してくれるため、投資初心者にとって最適な選択肢の一つです。本記事では、投資信託の基本的な仕組みから具体的な始め方、おすすめの商品選びまで、初心者の方でも理解しやすいよう詳しく解説します。
投資信託とは何か?基本的な仕組みを理解しよう

投資信託の基本概念
投資信託とは、多くの投資家から資金を集めて、その資金を投資のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などに分散投資し、運用成果を投資家に還元する金融商品です。「投信」や「ファンド」とも呼ばれます。
例えば、Aさんが10万円、Bさんが50万円、Cさんが30万円を出資したとします。合計90万円の資金をファンドマネージャーが様々な株式に投資し、1年後に100万円になったとしましょう。この場合、約11%の利益が各投資家の出資比率に応じて分配されます。
投資信託の種類と特徴
投資信託は大きく以下の種類に分けられます:
- インデックスファンド:日経平均株価やS&P500などの指数に連動することを目指すファンド
- アクティブファンド:ファンドマネージャーが独自の判断で銘柄選択を行い、指数を上回る成果を目指すファンド
- バランスファンド:株式と債券を組み合わせてリスクを抑えたファンド
投資信託のメリットとデメリット
投資信託の主なメリットは、少額投資が可能(100円から始められる証券会社も多い)、分散投資によるリスク軽減、プロによる運用などです。一方、運用管理費用(信託報酬)がかかる、元本保証がない、短期的には価格変動があるといったデメリットもあります。
2025年の投資環境と新NISA制度の活用方法

新NISA制度の概要と変更点
2025年から始まった新NISA制度により、投資信託への投資環境は大幅に改善されました。年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円の合計360万円となり、生涯投資枠は1,800万円まで拡大されています。
特に注目すべきは、売却した分の投資枠が翌年に復活する点です。例えば、100万円分の投資信託を売却した場合、翌年にはその100万円分の投資枠を再び利用できます。
2025年の市場環境と投資のポイント
2025年現在、世界経済は緩やかな成長基調にあり、特に米国株式市場は堅調に推移しています。日本でも企業の収益改善が続いており、投資信託による資産形成には良好な環境といえます。ただし、地政学リスクやインフレ動向には注意が必要です。
初心者におすすめの新NISA活用法
投資初心者の方には、まずつみたて投資枠を活用した積立投資をおすすめします。毎月一定額を自動的に投資することで、価格変動リスクを軽減できる「ドルコスト平均法」の効果が期待できます。例えば、毎月3万円ずつ投資すれば、年間36万円の非課税投資が可能です。
投資信託の選び方:初心者が注意すべきポイント

コスト面での選択基準
投資信託選びで最も重要な要素の一つがコストです。主なコストには以下があります:
- 信託報酬:年率0.1%~2.0%程度(インデックスファンドは一般的に0.1%~0.5%)
- 購入時手数料:0%~3.0%程度(ノーロードファンドは0%)
- 信託財産留保額:解約時に差し引かれる費用
例えば、100万円を年率1%の信託報酬のファンドに投資した場合、年間1万円のコストがかかります。長期投資では、このコスト差が大きな影響を与えるため、できるだけ低コストなファンドを選ぶことが重要です。
運用実績と安定性の確認方法
過去の運用実績も重要な判断材料です。ただし、過去の成績が将来を保証するものではないことを理解した上で、以下の点をチェックしましょう:
- 3年以上の運用実績があるか
- ベンチマーク(比較対象となる指数)との比較
- 同じカテゴリーの他のファンドとの比較
分散投資の重要性と実践方法
「卵を一つのかごに盛るな」という投資格言があるように、分散投資はリスク軽減の基本です。地域別(日本、先進国、新興国)、資産別(株式、債券、REIT)での分散を心がけましょう。初心者の方には、一つのファンドで世界中の株式に投資できる「全世界株式インデックスファンド」もおすすめです。
具体的な始め方:証券会社選びから購入まで
証券会社の選び方と比較ポイント
投資信託を購入するには証券会社での口座開設が必要です。2025年現在、主要なネット証券会社の特徴は以下の通りです:
- SBI証券:取扱ファンド数が最多(約2,600本)、Vポイントが貯まる
- 楽天証券:楽天ポイントで投資可能、楽天カードでの積立でポイント還元
- マネックス証券:マネックスカードでの積立で1.1%のポイント還元
口座開設から投資開始までの流れ
実際の投資開始までの手順を説明します:
- 証券会社のウェブサイトで口座開設申込み
- 本人確認書類の提出(オンラインで完結)
- NISA口座の開設申込み(同時申込み可能)
- 口座開設完了後、資金の入金
- 投資したいファンドの選択と購入
口座開設は通常1週間程度で完了します。マイナンバーカードがあれば、より迅速に手続きが進みます。
積立設定と購入タイミング
初心者の方には積立投資をおすすめします。例えば、毎月15日に3万円ずつ購入するよう設定すれば、あとは自動的に投資が継続されます。一括投資と比べて心理的負担も軽く、継続しやすいのが特徴です。
おすすめの投資信託3選と実例紹介
初心者向け定番ファンド
実例1:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
信託報酬0.1133%の低コストで、世界47か国の約3,000銘柄に分散投資できるファンドです。田中さん(30歳会社員)は2020年から毎月5万円ずつ積立投資を続け、5年間で約350万円を投資。2025年現在の評価額は約420万円となり、年平均リターンは約3.7%を記録しています。
米国株式重視のファンド
実例2:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国の代表的な500社に投資するファンドで、信託報酬は0.0968%です。佐藤さん(25歳)は新卒時から毎月3万円の積立を開始。3年間で約120万円を投資し、現在の評価額は約135万円。年平均リターンは約4.2%となっています。
バランス型ファンド
実例3:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
株式と債券、国内外の資産に均等分散投資するファンドです。山田さん(40歳)は安定性を重視し、毎月4万円を積立投資。2年間で約100万円を投資し、評価額は約105万円。リスクを抑えながら着実な成長を実現しています。
運用中の管理方法と注意点
定期的なポートフォリオの見直し
投資信託を購入した後も、定期的な見直しが重要です。年に1~2回程度、以下の点をチェックしましょう:
- 目標資産配分からの乖離
- ファンドの運用状況
- ライフステージの変化に応じた調整
感情に左右されない投資の継続
市場が下落した時に慌てて売却してしまう投資家が多いですが、長期投資では継続が何より重要です。2022年の市場下落時も、積立投資を継続した投資家の多くが2025年には含み益を回復しています。
税金と確定申告の基礎知識
NISA口座での投資であれば税金はかかりませんが、特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、利益に対して20.315%の税金が自動的に徴収されます。確定申告は基本的に不要ですが、損益通算を行う場合は申告が必要になることもあります。
よくある失敗例と対策方法
短期的な値動きに一喜一憂してしまう
投資信託の価格は日々変動します。しかし、短期的な値動きに過度に反応して売買を繰り返すと、手数料負けしてしまう可能性があります。長期的な視点を持ち、積立投資を継続することが成功の鍵です。
高コストなファンドを選んでしまう
銀行窓口で勧められるままに高コストなアクティブファンドを購入してしまうケースがあります。販売手数料3%、信託報酬2%のファンドと、ノーロードで信託報酬0.1%のインデックスファンドでは、長期的に大きな差が生まれます。
分散投資を怠ってしまう
特定の地域や業種に偏った投資をしてしまうと、その分野が不調になった時に大きな損失を被る可能性があります。地域、資産クラス、時間の分散を心がけましょう。
投資信託は初心者でも始めやすい投資手段ですが、基本的な知識と継続的な学習が重要です。2025年の新NISA制度を活用し、長期的な資産形成を目指しましょう。まずは少額から始めて、徐々に投資額を増やしていくことをおすすめします。市場の変動に惑わされず、自分の投資目標に向かって着実に歩み続けることが、投資信託での成功につながります。定期的な見直しを行いながら、無理のない範囲で投資を継続し、将来の豊かな生活の実現を目指してください。