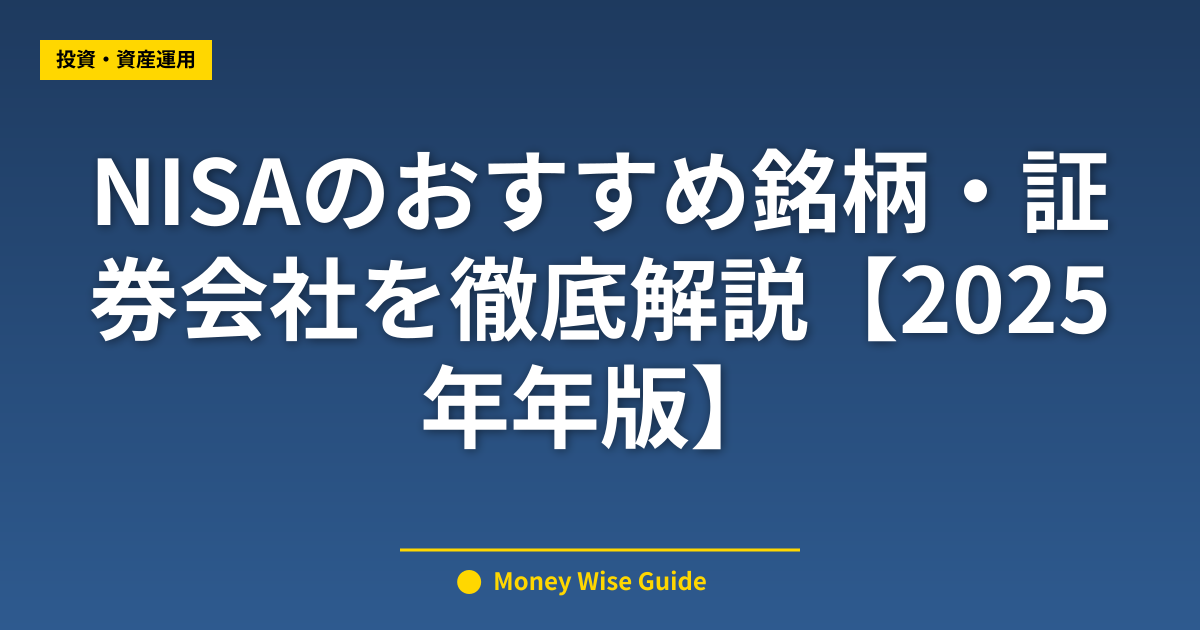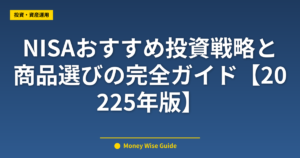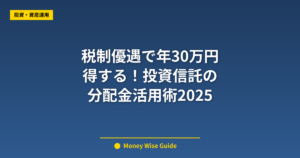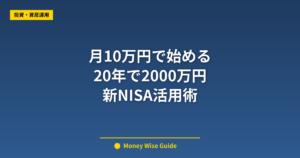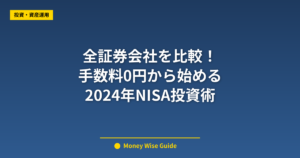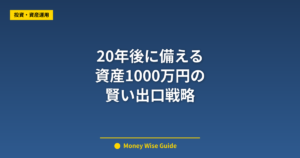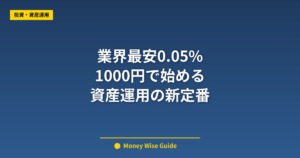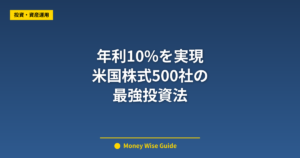NISAのおすすめ銘柄・証券会社を徹底解説【2025年版】
2025年から始まった新NISA制度により、投資環境は大きく変わりました。年間投資枠が360万円に拡大し、非課税保有期間が無期限になったことで、より多くの方が資産形成に取り組めるようになっています。しかし、「どの証券会社を選べばいいの?」「どんな商品に投資すべき?」といった疑問を抱く方も少なくありません。本記事では、2025年時点での最新情報をもとに、NISA活用のポイントから具体的なおすすめ商品まで、初心者にもわかりやすく解説します。
新NISA制度の基本を理解しよう

新NISAの投資枠と制度概要
新NISA制度では、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円の合計360万円まで投資できます。生涯投資枠は1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円までとなっています。
特に注目すべきは、売却した分の投資枠が翌年に復活する点です。例えば、100万円分の投資信託を売却した場合、翌年にはその100万円分の投資枠を再び利用できます。これにより、より柔軟な資産運用が可能になりました。
旧NISAからの変更点
旧制度と比較した主な変更点は以下の通りです:
- 年間投資枠:120万円→360万円
- 非課税保有期間:5年または20年→無期限
- 口座開設期間:2023年まで→恒久化
- 投資枠の再利用:不可→可能
NISA口座開設の注意点
NISA口座は一人一口座しか開設できません。また、年単位での金融機関変更は可能ですが、その年にすでに投資している場合は翌年まで変更できません。そのため、証券会社選びは慎重に行う必要があります。
おすすめ証券会社ランキング

総合力で選ぶトップ3
1位:SBI証券
投資信託の取扱本数が2,600本以上と業界最多水準で、クレカ積立のポイント還元率も最大5%と高水準です。三井住友カードでの積立なら、年間最大18,000ポイントを獲得できます。
2位:楽天証券
楽天カードでのクレカ積立により、投資額の0.5〜1%の楽天ポイントが貯まります。楽天経済圏を活用している方には特におすすめです。投資信託の取扱本数も2,500本以上と充実しています。
3位:マネックス証券
マネックスカードでのクレカ積立のポイント還元率が1.1%と高く、米国株の取扱銘柄数も4,000銘柄以上と豊富です。特に米国株投資を考えている方におすすめです。
手数料で比較する証券会社
国内株式の売買手数料は、多くのネット証券で無料化が進んでいます。SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券では、国内株式の現物取引・信用取引ともに手数料無料です。
投資信託の購入時手数料(販売手数料)についても、主要ネット証券では無料(ノーロード)が基本となっています。
サービス面での特徴
各証券会社のユニークなサービスも比較ポイントです。SBI証券では「かんたん積立アプリ」で手軽に積立設定ができ、楽天証券では「らくらく投資」で初心者向けのサポートが充実しています。マネックス証券では「MONEX VISION」で将来の資産予測ができます。
つみたて投資枠のおすすめ商品

インデックスファンドの王道3選
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
信託報酬0.05775%で、全世界の株式に分散投資できます。2025年の純資産総額は3兆円を突破し、多くの投資家から支持されています。初心者が最初に選ぶ一本としても最適です。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
信託報酬0.09372%で、米国の代表的な500社に投資します。過去20年間の年平均リターンは約10%と高いパフォーマンスを示しています。
楽天・全世界株式インデックスファンド
信託報酬0.192%で、楽天証券では楽天ポイントでの投資も可能です。バンガード社のETFを通じて全世界に投資します。
バランスファンドの選択肢
株式だけでなく債券も含めたい方には、バランスファンドがおすすめです。「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は、国内外の株式・債券・REITに8分の1ずつ投資し、信託報酬は0.143%です。
積立設定の実例
月30万円の投資枠を活用する場合の実例を紹介します:
- 全世界株式:月15万円
- 米国株式:月10万円
- バランスファンド:月5万円
このような分散投資により、リスクを抑えながら長期的な資産形成を目指せます。
成長投資枠の活用戦略
高配当株の選び方
成長投資枠では個別株投資も可能です。高配当株を選ぶ際は、配当利回りだけでなく配当の安定性も重要です。例えば、JT(日本たばこ産業)は配当利回り6%台ですが、業界の将来性を考慮する必要があります。
一方、NTTドコモやKDDIなどの通信株は、配当利回り3〜4%程度ながら安定した配当実績があります。過去10年間で減配していない点も評価できます。
成長株投資のポイント
成長株投資では、将来性のある企業を見極めることが重要です。例えば、AI関連企業やDX推進企業などが注目されています。ただし、個別株投資はリスクも高いため、投資額は総資産の10〜20%程度に抑えることをおすすめします。
アクティブファンドの選択肢
成長投資枠では、つみたて投資枠で購入できないアクティブファンドも選択できます。「ひふみプラス」や「さわかみファンド」などの日本株アクティブファンドは、長期的に市場平均を上回るリターンを目指しています。
年代別・目的別の投資戦略
20〜30代の投資戦略
若い世代は投資期間が長いため、株式中心のポートフォリオがおすすめです。全世界株式や米国株式のインデックスファンドを中心に、月10万円程度から積立投資を始めましょう。
実例として、28歳の会社員Aさんは、月15万円を全世界株式に投資し、3年間で約600万円の資産を築きました。市場の上昇局面もありましたが、継続的な積立投資の効果が現れています。
40〜50代の投資戦略
中年世代は教育費や住宅ローンなどの支出も多いため、リスクとリターンのバランスを考慮した投資が重要です。株式6割、債券4割程度のバランスファンドや、高配当株への投資も検討しましょう。
45歳の自営業Bさんは、月20万円をバランスファンドと高配当株に半々で投資し、安定したリターンを得ています。
60代以上の投資戦略
退職世代は資産の保全と安定した収益確保が重要です。高配当株や債券の比重を高め、株式は5割程度に抑えることをおすすめします。また、必要に応じて売却しやすい流動性の高い商品を選びましょう。
NISA活用の注意点と失敗例
よくある失敗パターン
NISA投資でよくある失敗として、「一括投資のタイミングを間違える」「手数料の高い商品を選ぶ」「短期売買を繰り返す」などがあります。
実例として、株式投資初心者のCさんは、2022年初頭に成長投資枠で個別株に一括投資しましたが、その後の市場下落で大きな含み損を抱えました。積立投資であれば、時間分散効果でリスクを軽減できたでしょう。
損益通算できない点に注意
NISA口座での損失は、特定口座や一般口座での利益と損益通算できません。そのため、リスクの高い投資は慎重に行う必要があります。
途中売却時の注意点
NISA口座で購入した商品を売却する際は、売却タイミングを慎重に検討しましょう。特に含み損がある状態での売却は、税制優遇を十分に活用できないことになります。
2025年の投資環境と今後の見通し
金融政策の影響
2025年現在、日本銀行の金融政策正常化が進んでおり、金利上昇局面にあります。これにより、債券投資の魅力が高まる一方、株式市場には一時的な調整圧力がかかる可能性があります。
新興技術への投資機会
AI、量子コンピューティング、再生可能エネルギーなどの分野で新たな投資機会が生まれています。これらのテーマに特化したETFやアクティブファンドも増加傾向にあります。
長期投資の重要性
短期的な市場変動に惑わされず、長期的な視点で投資を継続することが重要です。過去のデータを見ると、15年以上の長期投資では元本割れのリスクが大幅に低下しています。
新NISA制度は長期的な資産形成を支援する優れた制度です。2025年時点での投資環境を踏まえ、自分に適した証券会社と投資商品を選択し、継続的な投資を行うことで、将来の資産形成につなげましょう。重要なのは完璧を求めすぎず、まず始めることです。月1万円からでも積立投資を開始し、慣れてきたら投資額を増やしていく方法もあります。長期的な視点を持ち、市場の変動に一喜一憂せず、着実に資産形成を進めていくことが成功の鍵となります。