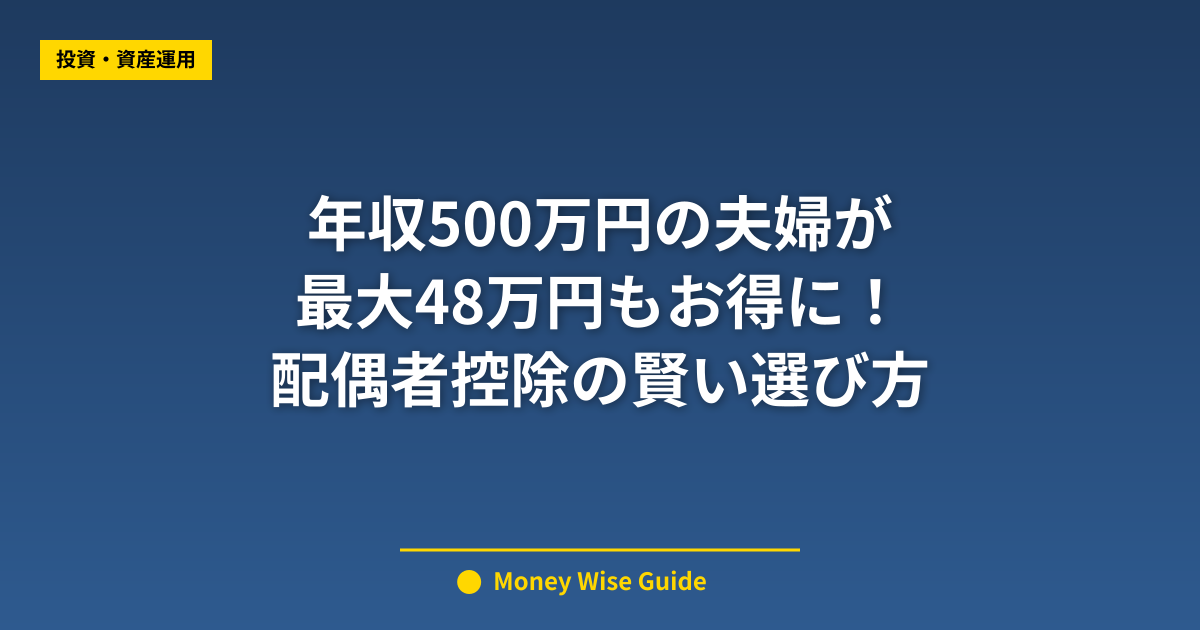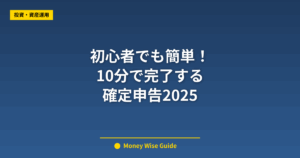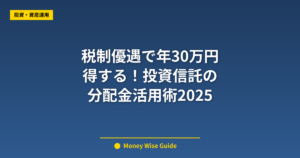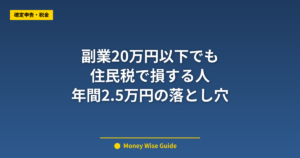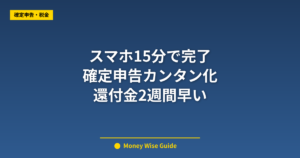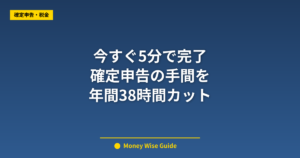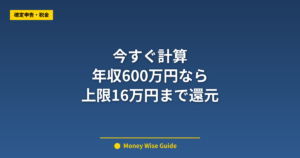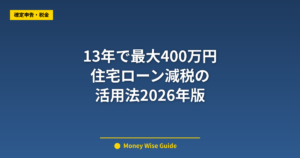配偶者控除と配偶者特別控除の違いと活用法【2025年版】
税金の計算で重要な役割を果たす配偶者控除と配偶者特別控除。名前は似ているものの、適用条件や控除額に大きな違いがあります。2025年現在、働き方の多様化に伴い、これらの制度を正しく理解することで年間数万円から十数万円の節税効果を得られる可能性があります。本記事では、両制度の基本的な仕組みから具体的な活用方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
配偶者控除の基本的な仕組み

配偶者控除の適用条件
配偶者控除は、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。2025年現在の適用条件は以下の通りです。
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
- 配偶者が白色事業専従者でない
控除額の詳細
配偶者控除の金額は、納税者本人の所得金額と配偶者の年齢によって決まります。
一般の配偶者控除
- 本人の合計所得900万円以下:38万円
- 本人の合計所得900万円超950万円以下:26万円
- 本人の合計所得950万円超1,000万円以下:13万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)
- 本人の合計所得900万円以下:48万円
- 本人の合計所得900万円超950万円以下:32万円
- 本人の合計所得950万円超1,000万円以下:16万円
実例:田中さんの場合
会社員の田中さん(年収600万円)の妻は専業主婦で収入がありません。この場合、田中さんの合計所得金額は約430万円となり、配偶者控除38万円を受けられます。所得税率が20%の場合、実際の節税効果は約7万6,000円になります。
配偶者特別控除の詳細解説

配偶者特別控除が創設された背景
配偶者特別控除は、配偶者控除の適用を受けられない場合でも、段階的に控除を受けられる制度です。これにより、いわゆる「103万円の壁」による就労調整を緩和する効果があります。
適用条件と控除額
配偶者特別控除の適用条件は以下の通りです。
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が他の人の扶養親族になっていない
控除額は配偶者の所得金額に応じて段階的に減少します。最大38万円から最小1万円まで、細かく設定されています。
実例:佐藤さんの場合
佐藤さん(年収700万円)の妻はパートで年収120万円です。妻の合計所得は55万円となり、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除31万円を受けられます。これにより約6万2,000円の節税効果があります。
2つの控除制度の違いと使い分け

適用される所得範囲の違い
最も重要な違いは、配偶者の所得範囲です。配偶者控除は所得48万円以下、配偶者特別控除は所得48万円超133万円以下が対象となります。つまり、配偶者の年収が103万円を超えても、201万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
控除額の推移
配偶者控除では所得48万円以下なら満額38万円ですが、配偶者特別控除では所得の増加に伴い控除額が段階的に減少します。このため、配偶者の収入が増えても急激に手取りが減ることはありません。
実例:山田さんの場合
山田さんの妻は2025年まで年収100万円のパートでしたが、2025年から年収130万円に増やしました。以前は配偶者控除38万円でしたが、現在は配偶者特別控除21万円を受けています。控除額は減りましたが、世帯全体の手取りは大幅に増加しました。
年収の壁と対策方法
103万円の壁の実態
「103万円の壁」は配偶者控除の適用ラインですが、実際には配偶者特別控除があるため、この金額を少し超えても大きな損失はありません。重要なのは段階的な変化を理解することです。
130万円の壁への対応
年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れる可能性があります。これは税制上の控除とは別の問題で、より大きな影響を与える場合があります。2025年現在、この壁への対策として以下の方法が考えられます。
- 年収を129万円以内に調整する
- 思い切って年収150万円以上を目指す
- 企業の社会保険適用条件を確認する
150万円の壁の意味
年収150万円までは配偶者特別控除の満額38万円を受けられます。つまり、税制上は103万円と150万円で大きな違いはありません。ただし、社会保険料の負担は別途考慮する必要があります。
申告方法と必要書類
年末調整での手続き
会社員の場合、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を申請できます。「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記入し、配偶者の所得を正確に申告します。
確定申告での手続き
自営業者や年末調整で申請できなかった場合は、確定申告で手続きします。配偶者の収入を証明する書類(源泉徴収票や支払調書など)を準備しておきましょう。
注意すべきポイント
申告時の注意点として、以下の項目があります。
- 配偶者の所得金額の正確な計算
- 本人の所得制限の確認
- 重複適用の防止(配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けられない)
2025年の制度変更と今後の展望
最近の制度改正の影響
2020年から基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられたことで、配偶者控除の適用条件も連動して変更されました。これにより、給与収入103万円以下という基準は維持されています。
働き方改革との関連
政府は働き方の多様化を推進しており、配偶者控除制度についても段階的な見直しが検討されています。2025年現在、大きな変更は予定されていませんが、将来的には制度の簡素化や統合が議論される可能性があります。
デジタル化への対応
税務手続きのデジタル化が進む中、2025年からは電子申告がより便利になっています。スマートフォンアプリでの申告や、AIを活用した自動計算機能なども充実してきました。
よくある質問と解決策
収入の計算方法がわからない場合
配偶者の収入には、給与だけでなく事業所得、雑所得なども含まれます。複数の収入源がある場合は、すべてを合計して判定します。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
年の途中で結婚・離婚した場合
配偶者控除・配偶者特別控除は、その年の12月31日時点の状況で判定されます。年の途中で結婚した場合は適用を受けられますが、離婚した場合は適用されません。
共働き夫婦の場合の注意点
夫婦ともに一定の収入がある場合、どちらが配偶者控除を受けるかは選択できません。所得の低い方が高い方の配偶者として控除対象になります。また、お互いに配偶者控除を受けることはできません。
結論
配偶者控除と配偶者特別控除は、適切に活用することで大きな節税効果を得られる重要な制度です。2025年現在、働き方の多様化に対応した柔軟な仕組みとなっており、配偶者の収入に応じて段階的に控除を受けられます。重要なのは、各家庭の状況に応じて最適な働き方と収入バランスを見つけることです。制度を正しく理解し、計画的に活用することで、世帯全体の手取り収入を最大化できるでしょう。